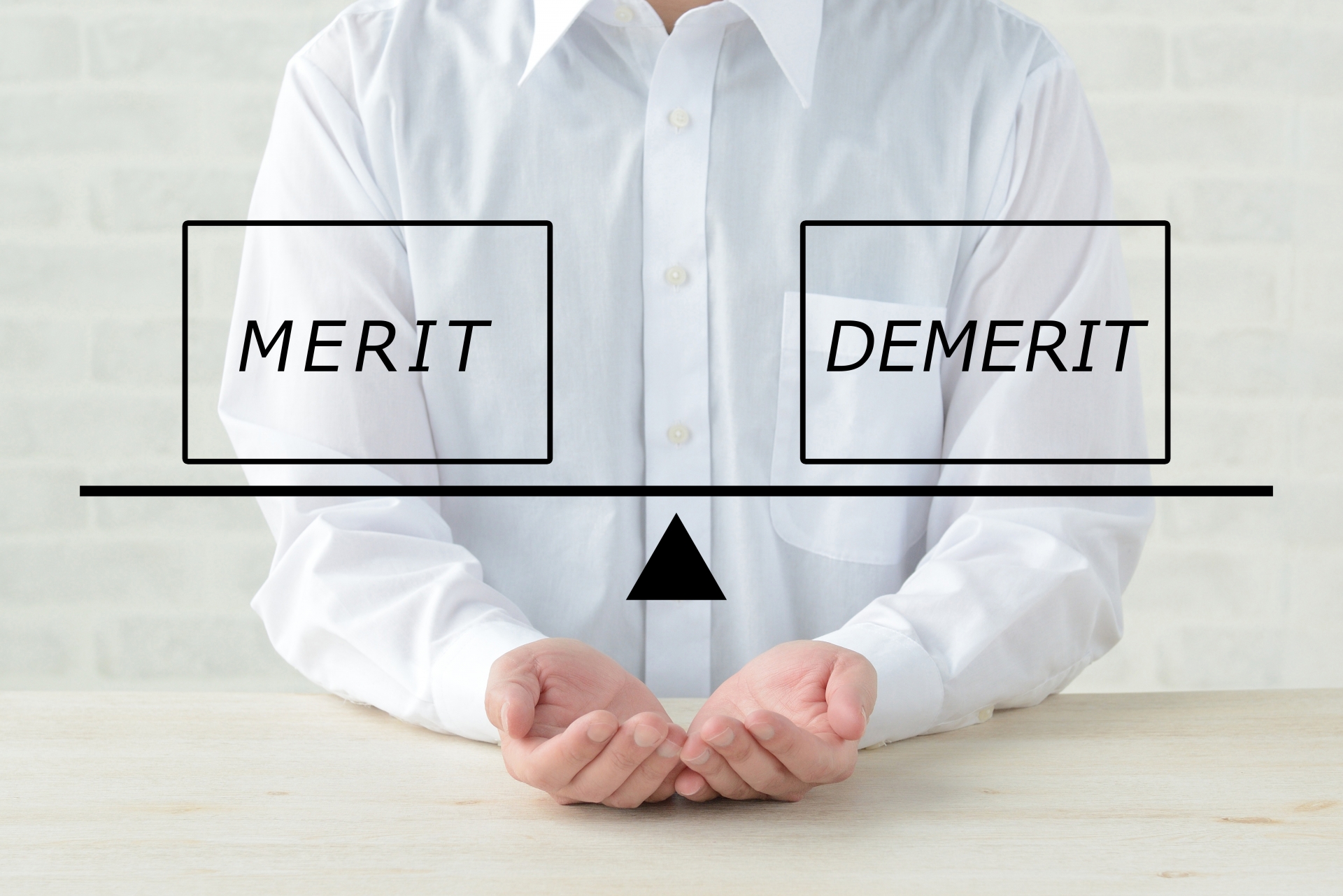経営者が上場を目指す興味や決心をすると、まず「何からやればいいのか?」と考えるはずです。
上場準備に関連する本を読むと『やらなければいけない事』はある程度、理解できるようになります。
しかし『何から始めるべきなのか』『どの順番でやればいいのか?』というのが、なかなか理解できないでいる方が多くいらっしゃいます。
ここでは上場準備の1番目と2番目に行う内容をズバリ説明させていただきます。
なお、あくまでもブログの中の人、個人のIPOコンサルティングにおけるポリシーのような見解でございまして、内容等を保証するものではありません。

上場準備は、反社会的勢力排除の取り組みから開始します
世の中には、IPOに関して、多くの本や情報があります。
いくつかのサイトを見ますと
- ショートレビューから始める
- 経営計画の策定から始める
- IPOコンサルタントの選定から始めるなど
がありました。
煽り文章ぽいので申し訳ありませんが、はっきり申し上げまして、ブログの中の人は、違うと思っています。
その主な理由は、次になります。
- ショートレビューから始める⇒後でも説明しますが、ショートレビューを始める前に行う事があります。
- 経営計画の策定から始める⇒定性的な計画を策定するのは否定しません。しかし定量的な計画(利益計画や資金計画等)は、月次決算を満足に作成できる会計組織構築が先です。月次での予実分析が出来ないような管理体制下で利益計画を作っても、全く意味が無いと考えています。会計組織の整備が先です。
- IPOコンサルタントの選定から始める⇒潤沢な資金を持つ会社以外は、金をかける対策からスタートするのは勇気が必要です。新規人材採用や外部支払コストがあまりかからない対策から始めましょう。
独特かもしれませんが、ブログの中の意見は、絶対に「反社会的勢力排除の取り組みから開始する」になります。
なぜなら、監査法人や証券会社等、外部専門家と契約を締結した後に、株主・主要取引先・役員等の中に反社会的勢力の存在が発覚した場合、上場の夢が終了してしまう可能性が爆増してしまうためです。
延期ではありません。終了です。
例えば、経営管理能力が低いとか、業績が悪いというような会社の場合、監査法人や証券会社は、「経営管理能力が上がったとき、上場を目指しましょうね」または「業績が良くなった時、上場を目指しましょうね」といった話になりますが、「反社会的勢力と関係を絶ってから上場を目指しましょうね」という言葉は一切出てきません(キッパリ)。
つまり、上場準備の再出発がありません。
さらに例えば、三菱UFJ証券や日興証券、みずほ証券を主幹事として上場準備を開始して、その途中に反社との強い関係が見つかった場合、証券会社だけではなく、同じグループの銀行にもその情報が流れてしまう可能性が高いと思っておいた方がいいです。つまりそれは、上場準備どころか、経営危機が訪れてしまう危険性が出てくると考えるべきです。
少なくとも監査法人や証券会社等、外部専門家と契約を締結する前に、反社会的勢力との関係を完全に絶っておくことが必須になります。
「反社チェックは、主幹事証券会社が入ってから開始した会社が上場達成した事例を知っているぞ!」「反社チェックを1番目に始めた会社なんて無いぞ!」とお考えの方はいらっしゃると思います。
もちろん、ブログの中の人も知っています。
しかし、それはたまたま、その会社が反社会的勢力と取引等を行っていなかったからにすぎません。
ブログの中の人は、不幸な会社を何社も見ています。
反社との関係を持っている会社が、一生懸命、経理や開示の体制を整備しても、株式上場には一歩も近づけません。
反社会的勢力排除のための取り組みについては、↓のブログ記事があります。ご参考下さい。
上場準備を始めると決心したら、まず反社排除に向けた取り組みを行い、問題無いと判断してから、次のステップに進みましょう。
もし反社との関係に問題が判明すれば、その問題を完全解決してから、次のステップに進みましょう。
社内における稟議システムを企業文化に根付かせる(2023/1/11追加)
ブログの中の人は、反社会的勢力排除の取り組みの次に徹底すべき事項として、稟議システムの運用と記録の徹底です。
口頭で社長にOK貰えば、何でも買えるという企業文化から、意思決定の状況をしっかりと記録するという企業文化への変更は、全社で取り組みが必要であり、社内で反発を招くケースがよくあります。
上場を目指すためには、職務分掌を明確にし、決裁権限を一定以上分散させる事になりますが、スタート時点では決裁権限を社長へ集中させることもやむを得ないと思います。
反社チェックのプロセスを組み入れた稟議システムの整備・運用を開始しましょう。
稟議について書いている記事は↓になります。ご参考ください。
業界内での事件・事故・問題・課題の棚卸と対策をする
上場準備を開始すると、まず監査法人、次に証券会社から、きっと数多くの指摘を受けることになります。
ただし10個の指摘を受けたとしても、それぞれの指摘の中には、間違いなくレベル感があります。
上場準備の初期段階の会社において、課題にあって当然なのは、適時開示体制です。
当たり前です。上場準備初期段階から適時開示体制が万全状態な会社とは、子会社上場、またはリクルートや第一生命、日本郵政等の馬鹿デカいIPOくらいであり、一般的なスタートアップ企業の上場準備の初期段階で、適時開示体制が課題として指摘されても、凹む事は一切ありません。
一方、監査法人や証券会社が「え~~~??そんな事さえ何もやってないのぉ??」と思われるような事が続出すれば、一気にゴミ案件として認定されます。
それは業界内での事件・事故・問題・課題に対して、対策をしていなかった、または対策が乏しいと思われるケースです。
また許認可の維持継続に向けた取り組みがプアであると思われるケースです。
わかりやすいところで申しあげますと、例えば福祉関係の業界では最近、虐待事件が絶えません。福祉関係の会社であるにも関わらず、虐待防止対策をキチンと回答できない場合、速攻でゴミ案件化するということです。
さらに、あくまでも上場を目指す会社にあたっては、外部の第三者に対応ぶりを認められなければならないという意識を持つ必要があるため、対策内容や状況を”可視化”することが必須になります。「対策しました。しかし、関係資料は全部廃棄しました。」ではアウトです。
ブログの中の人は、上場を目指す会社の場合、上場に向けた自社独自に存在する問題や課題等よりも、業界全体に蔓延る問題や課題に関する対応対策を優先すべきと考えています。なぜなら、外部の人間が個社特有の問題から指摘や調査を開始、または重要視するとは、考えにくいと思うためです。
さらに例えば、関連当事者取引は自社独自の課題として対応が必要になりますが、ほとんどの関連当事者取引は企業存続に即時影響しません。
しかし、業界全体に蔓延る問題や課題が事件として起きてしまえば、企業存続に直結します。どちらを優先しなければいけないのかは、明確です。
業界に関しては、監査法人や証券会社は完全に素人です。業界のプロが素人に問題課題を指摘されるような事にならないようにしましょう。
各業界にどのような問題が蔓延っているのかを知る手段は、いくつも存在すると思いますが、ひょっとすれば、リスク情報の調査がヒントになるかもしれません。
IPO AtoZでは、上場達成企業のリスク情報についてデータ化しております。
少し古い記事ですが、そのデータを利用した記事を↓に紹介します。
手前味噌ながら、おそらく現段階で日本国内にこんな面倒な事をしている人って、ブログの中の人だけだと思います。
ぜひ、オンラインサロンでご質問ください。
監査法人担当者から評価される体制づくりを行います
上場準備に関する100万単位のまとまったコストをかけることになる最初のプロセスは、監査法人によるショートレビューになります。
ショートレビューは、単にIPOに向けた課題を抽出するためのプロセスとして捉える人がいます。
ブログの中の人の考えは、若干異なります。まずはその理由からお話しさせていただきます。
ショートレビューとは、上場に向けた課題の抽出のプロセスだけではない
ブログの中の人は、某証券会社の公開引受部門に在籍した経験があります。
証券会社と主幹事契約を締結した会社の中で実際に上場出来たのは、5社に1社もありませんでした。
つまりブログの中の人の経験からすれば、【上場達成会社数/主幹事契約した会社数】は20%未満です。
【上場達成会社数/ショートレビューを実施した会社数】は、【上場達成会社数/主幹事契約した会社数】よりも低い数字であることは間違いありません。
一方、会計士にとりまして、監査担当先の上場達成社数のトラックレコードはキャリア形成の一つであることも間違いありません。
ご存じの通り、監査法人の会計士は労働過多と言われる状況下にあり、履いて捨てるほど案件が舞い込んできている状態です。
そんな状況下であるため、会計士自身の個人リソースは、「IPO出来る可能性のある会社」と「IPOが出来る可能性が低い会社、または面倒な会社」では大きく異なると考えられます。
以上のような理由から、ブログの中の人は、監査法人担当者にとりまして、ショートレビューを「IPO出来る可能性のある会社」と「その他の会社」で仕分けし、どこの会社に自分自身のリソースを割くのかを選別するプロセスであるとして認識した方が良いと考えております。
つまりショートレビューには、上場審査的な要素が含まれていると考えるべきです。
上場を目指す会社の経営者は、ショートレビューを単にIPOに向けた問題を洗い出すためのプロセスとして捉えるのではなく、ショートレビューを通じて最低限「この会社、ひょっとしたらIPO出来るんとちゃうか?」と監査法人担当者に思わせなければIPOは無理というような厳しい態度で臨むべきと考えています。
会計士は、担当会社を公平に個人的なリソースを割くことをしないと思います。
これはきっとビジネスマン全般に言えることであり、例えば銀座のクラブだって、一見さんで見た目から貧乏な私なんかより、得意客や有名企業役員等にリソースを割くと思います。
この考えは、監査法人の会計士にも間違いなく存在すると考えられます。
【上場達成会社数/ショートレビューを実施した会社数】は、どの程度なのかわかりませんが、仮に20%であると仮定すると、一定以上の好印象を監査法人担当者に持たせなければ、上場達成できないと考える必要があります。
「会計監査を受けようとしたときの事前準備のポイントと例示」を読む
日本公認会計士協会は、「株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブック」という書面を発行しておりまして、その9ページ以降に「会計監査を受けようとしたときの事前準備のポイントと例示」という章が存在します。
「会計監査を受けようとしいたとき」とは、ブログの中の人は、「ショートレビューを受けるとき」として理解しています。
したがいまして、上場準備の初期段階のプロセスは、次のようになります。
- 反社排除に向けた取り組みを行う
- 業界内での事件・事故・問題・課題の棚卸と対策をする
- 「株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブック」を読む
- 「株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブック」の9ページ以降を対策し、ショートレビューの段階で監査法人担当者から評価される体制を作る
- ショートレビューを行う
このブログ記事を書いたきっかけは、上の1.~3.までのプロセスについて説明したサイト等が存在しなかったためです。
「会計監査を受けようとしたときの事前準備のポイントと例示」の解説
ここでは、日本公認会計士協会 株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブックにある「会計監査を受けようとしたときの事前準備のポイントと例示」の各項目について、ショートレビューを受けるまで、会社の管理がどのレベルに到達している必要があるのかを簡単に説明させていただきます。
あえて、ブログの中の人の個人的な意見であることを繰り返し申し上げさせていただきます。
表現は、あえて多少キツイ表現をしています。
会計データ・裏付け証憑の整理
10ページと11ページの箇所になります。この箇所では以下のような事が述べられています。
「納品書、検収書、請求書などの証憑書類が体系的に整理されていないので、証憑書類が会計処理に対応していない、後から追跡できない、または、全てが揃っていない。」ということはありませんか。
(出所:日本公認会計士協会 株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブックより)
ショートレビューにおきまして、上記のような事項について改善を指摘されるよう場合、「こんな会社は上場できんわ」という評価になります。
ショートレビューを受けるまでに、完璧に仕上げておきましょう。
発生主義会計及び収益認識会計基準への対応
12ページ~14ページの箇所になります。この箇所では以下のような事が述べられています。
- 現時点で、現金主義に基づいて会計処理している項目はありませんか。
もしある場合、発生主義及び収益認識会計基準を適用して会計処理を行うために必要となる情報は整理されていますか。(出所:日本公認会計士協会 株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブックより)
現金主義で会計処理をしている会社は、はっきり申し上げまして、ショートレビューにコストをかける意味がありません。
収益認識会計基準については、監査法人と議論になる項目です。ショートレビューを受ける前には、収益認識について経理責任者や担当者だけではなく、経営者も学習し、監査法人と収益認識について、会話が出来るレベルになっておきましょう。
販売取引について、会社が果たすべき機能・役割や顧客との取引条件は整理されていますか。
(出所:日本公認会計士協会 株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブックより)
取引条件の整理は勿論必須です。なお、取引基本契約書が営業マンの個人の机の中に入っている等、バラバラに保管されているような状態であれば、N-3に入れません。
棚卸資産管理
15ページ~16ページの箇所になります。この箇所では以下のような事が述べられています。
- 「在庫の実地棚卸をやっていない。」、又は「実地棚卸はやっているが、精度は十分ではない。」ということはありませんか。
- 「実地棚卸をやっているので、在庫の受払記録は作成していない。」ということはありませんか。
(出所:日本公認会計士協会 株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブックより)
ショートレビューの段階で棚卸資産管理について、このレベルを指摘されるような会社は、はっきり申し上げまして、ショートレビューを受ける意味がありません。
ショートレビューまでに完璧に仕上げておきましょう。
原価計算体制
17ページの箇所になります。この箇所では以下のような事が述べられています。
「人件費やその他の経費を、発生の都度、費用処理している。製造番号やプロジェクトごとの作業工数の集計もしていない。」ということはありませんか。
(出所:日本公認会計士協会 株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブックより)
会計監査が開始した後、ほとんどの会社では、原価計算が最初の議論がされます。
ショートレビューまでに原価差異分析を複数回行い、課題を見つけ、具体的な対策内容を監査法人へ説明出来るようにしましょう。
製造番号やプロジェクトごとの作業工数の集計もしていないような会社は、N-3にさえ入れません。
資産・負債の管理
18ページと19ページの箇所になります。この箇所では以下のような事が述べられています。
- 「固定資産台帳には載っているが、現物に管理番号は付していないし、現物の置き場所も頻繁に変更しているので、台帳上の資産がどこにあるのか、そもそもあるのかないのかが分からない。」ということはありませんか。
- 「売掛金、未収入金、立替金、仮払金」などの資産項目に限らず、「買掛金、前受金、仮受金」などの負債項目の勘定明細の中に、以前から「その他」などで括られたものがあり、今となってはその内容の分からないものがある。」ということはありませんか。
(出所:日本公認会計士協会 株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブックより)
ショートレビューを受ける前に固定資産の実地棚卸をしましょう。もし不明資産が存在すれば、損失計上額を見積もり、銀行借入に影響が出ないかどうかを確認するとともに、再発防止策の検討し「これから・・・・を対策するので、こんな事は二度とありません!」と監査法人へ言えるようにしましょう。
負債項目の勘定科目の中に「その他」などで括られたものがあれば、説明出来るようにしましょう。説明出来ないと相当ヤバいと思います。
連結決算
20ページと21ページの箇所になります。この箇所では以下のような事が述べられています。
- 「当社のほか、当社の役員が支配しているグループ会社が存在するなど、『当社が支配している会社』(子会社)を特定することが難しい。」ということはありませんか。
- 連結子会社から、連結決算を行うために必要となる正確な情報を迅速に入手できますか。
(出所:日本公認会計士協会 株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブックより)
ショートレビューを受ける前までに、子会社、関連会社、関係会社を明確にしましょう。
また「連結パッケージは、これじゃぁ!」とドヤ顔で言えるようにしましょう。
子会社、関連会社、関係会社については、↓をご参考ください。
関連当事者取引の把握・整理
22ページの箇所になります。この箇所では以下のような事が述べられています。
- 関連当事者との取引は網羅的に把握・整理されていますか。
- 親会社、兄弟会社、主要株主、当社の役員、当社の役員が支配している会社、役員の親族や親族支配の会社等との取引はありませんか。
(出所:日本公認会計士協会 株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブックより)
まずショートレビューを受けたとき、管理部門責任者が関連当事者という用語を初めて聞くような状態では、N-3は厳しいと考えます。
ショートレビューに入る前に関連当事者の範囲を把握しましょう。↓をご参考ください。
ショートレビューには、「関連当事者は、この個人法人です。そして関連当事者等の”等”に該当する人は、この個人法人です(または”等”に該当する人はおりません)」と言えるような準備をしておきましょう。
そしてショートレビューまでに取引の有無を事前調査しましょう。もし関連当事者と取引をしていれば、ショートレビューを受ける前に契約内容や取引内容・取引理由をサクサクっと説明できるようにしましょう。
内部管理体制の構築
23ページの箇所になります。この箇所では以下のような事が述べられています。
属人的ではなく、上場会社として求められる事業運営を行っていますか。
(出所:日本公認会計士協会 株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブックより)
スタートアップ企業であれば、属人的な事業運営を行っている事は、仕方ないと思います。
ショートレビューの時に「リスク情報に、属人的な事業運営に関する内容を書こうと考えています」「属人的な事業運営から脱却するために〇や×のような取り組みをしています」と言えるような準備をしておきましょう。
横の兼務や縦の兼務については、↓をご参考ください。
必要な内部管理体制を整備し、運用するための仕組みや人材に投資していますか。
(出所:日本公認会計士協会 株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブックより)
最低限、ショートレビューまでに規程を整備し、運用を開始しておきましょう。
もし、人材投資に関して上手く回答出来なかった場合、「企業内容等の開示に関する内閣府令の改訂が行われました(行われます)。多くの上場会社が人材育成方針等を開示することになりますので、その情報を参考にして、方針等を今後考えていきたいと思います。」とその場をしのぐ回答をおススメします。
↓をご参考ください。
労務管理
24ページの箇所になります。この箇所では以下のような事が述べられています。
残業代の支払漏れなど、決算に影響を与えるような労務管理上の課題はありませんか
(出所:日本公認会計士協会 株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブックより)
ショートレビューまでに、最低限、労務管理について課題の洗い出しと対策に着手しておきましょう。
専門の社労士に人事労務のデューデリジェンスをしてもらうことをおススメします。IPO AtoZは、専門の社労士を紹介しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
情報システムの内部統制
25ページと26ページの箇所になります。この箇所では以下のような事が述べられています。
- 会社の情報システムに関連するIT全社統制を構築していますか。
- また、会社のIT全般統制である、情報システムについての内部管理体制の整備と運用も行っていますか。
- 会社外部の業者が提供するITサービスについても、社内の情報システムと同様に、安全にデータを管理しなければなりませんが、体制が整っていますか。
(出所:日本公認会計士協会 株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブックより)
ショートレビューを受けるまでに、情報システムに関連する管理規程整備した上で、規程の運用状況を監視・監督し、課題や改善策があれば、それを整理し、監査法人へ説明できるように準備しましょう。
不正への対応
27ページと28ページの箇所になります。この箇所では以下のような事が述べられています。
役職員の不正を防止するために、過剰なプレッシャーをやめ、牽制が働く内部管理体制を整えていますか。
(出所:日本公認会計士協会 株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブックより)
最低限、「出納担当者」と「記帳担当者」を分離出来ている組織を形成してから、ショートレビューに入りましょう。
従業員数に関係なく、ショートレビュー前に内部通報制度を導入することを強くお勧めします。
会計上の見積り
29ページの箇所になります。この箇所では以下のような事が述べられています。
将来の見積りを考慮した会計処理が求められる項目が多くありますが、その見積り金額の算出方法などの検討プロセスを整備していますか。
(出所:日本公認会計士協会 株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブックより)
ショートレビューまでに年金数理人(退職給付債務)や不動産鑑定士・企業価値評価専門家(固定資産の減損会計等)等、専門家と事前に契約しておきましょう。「正確な財務諸表を作成するため、こんなにバックがついてます」と監査法人にドヤ顔で言えるようになれば、評価はウナギ上りです。
会計基準の選択
30ページと31ページの箇所になります。この箇所では以下のような事が述べられています。
上場会社は、企業会計基準委員会が公表した会計基準(日本基準)のほかに、IFRS基準を選択できますが、会社にふさわしい基準を検討していますか。
(出所:日本公認会計士協会 株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブックより)
これより、上で取り上げた12個の項目の方が重要です。
まとめ
上場準備の初期段階に行う内容を説明させていただきました。
今、監査法人は、履いて捨てるほど、案件が舞い込んでいます。
株式上場とは、監査法人、証券会社、東京証券取引所の3法人に認められた会社だけが達成できます。
はっきり申し上げまして、今は、直接プライム市場へ上場出来そうなユニコーン企業を除き、監査法人や証券会社、東証よりも、上場を目指す会社の方が立場的に弱い現状です。
つまり、ブログの中の人は、上場を目指す会社側の意見や希望等を考えるだけで上場準備を進めていくのではなく、監査法人担当者はどう考えているのか、証券会社担当者はどう思っているのかを常時意識しながら、初期段階から上場準備作業を進めていく必要がある事を伝えたくて記事にさせていただきました。
上場準備の最初のハードルは、ショートレビューを通じた監査法人監査担当者個人からの評価になると考えています。
もうすでに上場準備を行っている会社関係者の方々の中には、監査法人の対応が不満な方がいらっしゃると思います。
それはひょっとすると、会計士からショートレビューの段階で「こんな会社上場出来へんわ」と評価されてしまっているかもしれません。
IPOAtoZでは、上場準備に関しまして、色々なご質問を承っております。
例えば、このブログ記事にある『会計監査を受けようとしたときの事前準備のポイントと例示』にある13項目に関するご質問なども承っております。
ブログの中の人は、上場支援業を行っております。また上場支援関係者の方とコラボも積極的に行っております。
ぜひ↓のフォームからお気軽にお問い合わせください。
IPO AtoZでは、Twitterで情報発信しております。ぜひフォローをお願いします。
重ねて申し上げますが、あくまでもブログの中の人の個人意見でありまして、内容等を保証するものではありません。