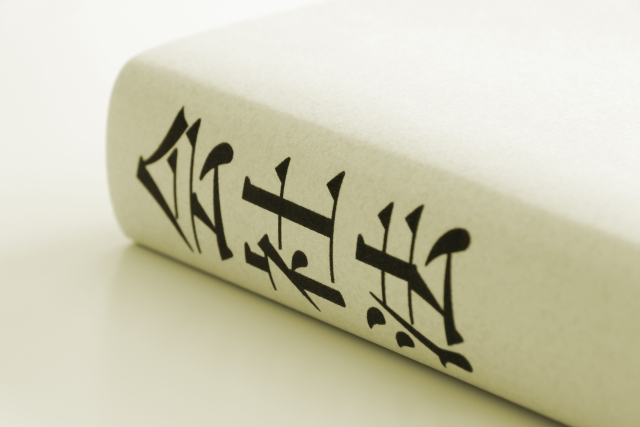スチュワードシップ・コードとは
機関投資家が責任のある機関投資家として、あるべき姿を規定した指針です。
この指針は、投資先企業の企業価値を向上して、受益者の利益を最大化するために設けられています。
日本におけるスチュワードシップ・コード(「日本版スチュワードシップ・コード」といいます)は、8つの原則(令和2年5月段階)、そして各原則のもとにある指針で構成されています。
- 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
- 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
- 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
- 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
- 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
- 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
- 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
- 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。
スチュワードシップ・コードの詳細については、こちらになります。
スチュワードシップ・コードとコーポレートガバナンス・コード
スチュワードシップ・コードと類似する用語として、コーポレートガバナンス・コードがあります。
どちらも経済の持続的成長の促進を目指す企業行動規範であることが共通しており、密接に関係しています。
最も大きな違いは、次のとおりになります。
- スチュワードシップ・コード・・・機関投資家向け
- コーポレートガバナンス・コード・・・上場会社全般向け
コーポレートガバナンス・コードについては、こちらで説明しています。
スチュワードシップコードとESG
スチュワードシップコードの原則1は次のようになっており、その原則に繋がる指針には次のような一文が存在します。
【原則1】
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
【指針1-1】
機関投資家は、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティ(ESG 要素を含む中長期的な持続可能性)の考慮に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)などを通じて、 当該企業の企業価値の向上やその持続的成長を促すことにより、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図るべきである。
つまり、機関投資家は投資先企業との間でESGに関する対話を推進すべきということであり、またこれは、機関投資家はESGに無関心な会社に投資すべきではないという事と同じように扱われています。
ESGとは何かということを次で説明しています。