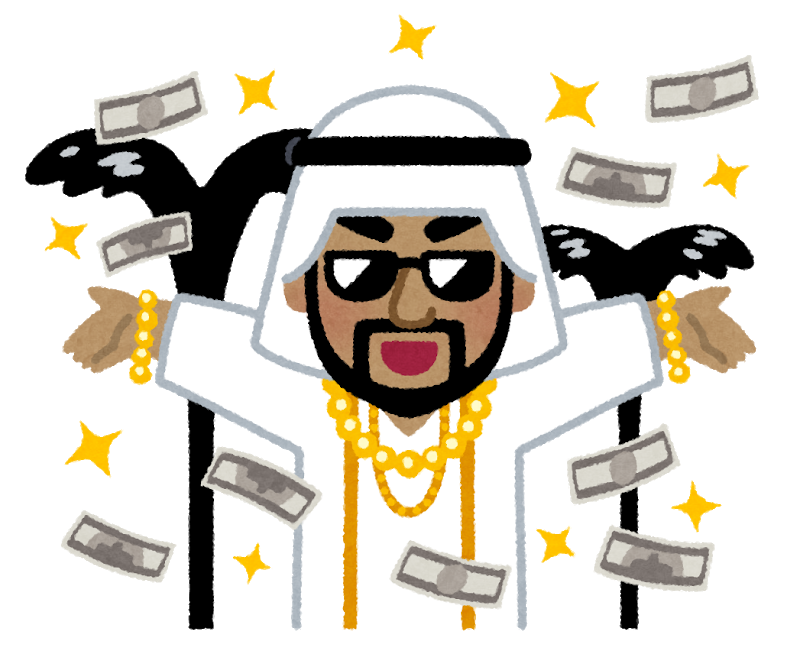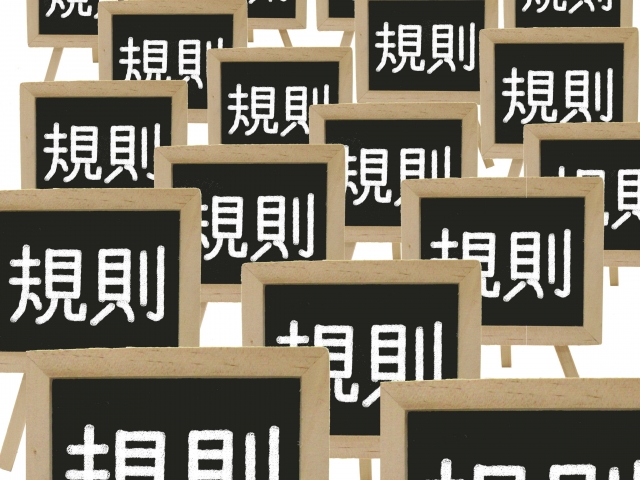
令和6年において、税制適格ストックオプションに関する税制改正が行われました。
その中で、権利行使された株式が譲渡制限株式の場合、発行会社が管理できるようになるという改正がありました。
つまり、会社は税制改正がある前まで、税制適格ストックオプションを権利行使して取得した株式を金融商品取引業者(証券会社または信託銀行)に管理を委託する必要がありましたが、株式が譲渡制限株式である場合、自社管理がOKとなったという改正です(税務上では、従前から自社管理が可能(ストックオプションに対する課税(Q&A 令和5年7月)より)でしたが、支援対応してくれる金融商品取引業者が存在しなかったので、実務的に自社管理ができなかったが正しい表現かもしれません。)。
そこで、経営者は「外部支払コストが減ったぁ!」と考えるかもしれませんが、喜ぶのはまだ早いです。
証券会社が行っているような実務を発行会社自身で行う必要が出てくるのです!
この記事では、非上場会社で役職員等が税制適格ストックオプションを権利行使し、それ以降、証券会社等に委託することなく、その会社だけで手続きを完結する場合、どのような株式事務が発生するのかを私なりにまとめてみました。
しかしご注意頂きたい事項があります。
- 租税特別措置法、租税特別措置法施行令、租税特別措置法施行規則および令和6年経済産業省告示第69号を配慮した株式事務を書いており、会社法上(例:株式譲渡制限会社における取締役会決議等)や商業登記法上(例:新株予約権権利行使の際の変更登記等)、上場審査を考慮して必要となる実務(例:特別利害関係者等が株式譲渡した際の開示等)、会計(例:新株予約権権利行使に伴う仕訳業務等)などにつきましては、配慮しておりません。
- 記事の内容に保証等はできません。最終的には顧問税理士や管轄の税務署などの専門家におたずねください。
事務1:税制適格ストックオプションを権利行使する
税制適格ストックオプションを権利行使する際、権利行使者が一般的には、「新株予約権行使請求書」という書面を発行会社に提出します。
「新株予約権行使請求書」のフォーマットにおける、税法上・実務上で必要となると考えられる項目は、表1のような内容になります。
表1 「新株予約権行使請求書」に必要になる項目
| 新株予約権行使請求書に必要な項目 | 例 | |
|---|---|---|
| 1 | 新株予約権を権利行使する人の氏名と住所 | 〇〇〇〇 〇県〇市〇町〇-〇-〇(住所は、納税地) |
| 2 | 新株予約権を権利行使する日 | 令和〇年〇月〇日 |
| 3 | 権利行使する新株予約権の名称 | 〇〇株式会社 第〇回新株予約権 |
| 4 | 権利行使する新株予約権の個数 | 〇個 |
| 5 | 新株予約権の付与決議の日において、大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しない誓約 | 私は、行使する新株予約権に係る付与決議の日において租税特別措置法第29条の2第2項第1号に定める貴社の大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しないことを誓約します。 |
| 6 | (権利行使者が社外高度人材の場合)
認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施時期の開始等の日から当該行使の日まで引き続き居住者であつた誓約※ |
私に係る中小企業等経営強化法に規定されている認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施時期の開始等の日から、新株予約権を権利行使する日まで引き続き居住者であったことを誓約します。 |
| 7 | 新株予約権の行使の日の属する年における当該権利者の他の特定新株予約権の行使の有無※※ | 「有」or「無」 |
| 8 | (権利行使者が承継相続人である場合)
権利の被相続人に関する事項 |
「被相続人の氏名:〇〇〇〇」
「死亡の時における住所:〇県〇市〇町〇‐〇-〇」 「死亡年月日:〇年〇月〇日」 |
| 9 | 新株予約権を権利行使する人のマイナンバー※※※ | 「1234567891023」 |
※ 発行会社は、社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定の取消しが無かった事実を記載・記録を要します。
※※ 権利行使者が他の会社でストックオプションの権利行使を行っている可能性もあります。この箇所でその確認することになります。「有」と記載された場合、「付与会社の名称」 「付与会社の本店所在地」「行使年月日」「権利行使価額」を追記してもらいます。
※※※ 特に社外の人にマイナンバーを徴求するにあたっては、社内の規程等を確認した上、実行しましょう。会社によっては、新株予約権行使請求書のフォーマットに掲載すべきではない会社が存在するはずです。注意しましょう。
「新株予約権行使請求書」のフォーマットは、一般的に、いわゆる「株懇モデル(こちらになります。しかし会員限定になっています。)」を参考にして、利用することをお勧めします。なお、「新株予約権行使請求書」をググると、古いモデルが検索されるので、丸写しするのはやめましょう。
証券会社に依頼して「新株予約権行使請求書」のフォーマットを依頼してみるのも良い方法だと思います(株式を入庫希望する証券口座番号に関する内容が存在しますが、その項目内容を削除するだけで使えると思料しています)。
また、権利行使請求をした時の書面等は、提出を受けた日の属する年の翌年から5年間保存が義務化されています(租税特別措置法施行規則第11条の3第6項)。
さらにこの手順は、従前、権利行使の請求に関し、書面の提出が義務化されていましたが、令和6年税制改正において、電磁的方法による請求が認められるようになりました。
さらに後述する「事務3」で紹介する「区分管理帳簿」の写しを交付する必要があります。
事務2:発行会社が株式を交付する
これは、従前と同じプロセスであり、変更はありません。
権利行使する人が銀行に権利行使価額を入金し、発行会社が入金を確認した後、株式を交付します。
一般的には、「新株予約権行使請求書」のフォーマット内に「入金確認」の押印箇所があり、発行会社が入金確認すると、その箇所に押印して、株式を交付します。
事務3:発行会社が株式を管理する
前述のとおり、これまで発行会社は、金融商品取引業者(主に証券会社)と株式保管の委託契約を締結し、金融商品取引業者に管理を委託しなければいけなかったのですが、この度、株式が譲渡制限株式に限り、その契約および委託を要せず、自社で管理できることになりました。
したがいまして、ここからが令和6年税制改正において発生する株式実務の変更箇所になります。
区分管理帳簿の記載内容
まず「区分管理帳簿」を作成して、他の株式とは別に管理する必要があります。
ストックオプションを発行すると会社法249条で定められた「新株予約権原簿」を作成することになりますが、新株予約権原簿のほとんどは「回号別」で作成されています。
一方、「区分管理帳簿」は、「税制適格ストックオプションを行使した人別」に作成し、帳簿を閉鎖した年の翌年から5年間保存することになります(令和6年経済産業省告示第69条第1条3項)。
「区分管理帳簿」のフォーマットには、表2のような事項を記載することになります。
なお、
- 「税制適格ストックオプションを権利行使して取得した株式」:A株式
- 「相続等で承継された株式が、被相続人等によって税制適格ストックオプションを権利行使して取得した株式」:B株式
としています。
表2 「区分管理帳簿」の記載内容
| 記載する内容 | 例 | 条文※ | |
|---|---|---|---|
| 区分管理帳簿作成日 | 〇年〇月〇日 | 1-1 | |
| 権利者の氏名と住所 | 〇〇〇〇 〇県〇市〇町〇‐〇‐〇 | 1-2 | |
| 株式に係る事項 | A株式とB株式の区別 | 特定株式・特定承継株式 | 1-3-イ |
| 株式の種類 | 普通株式・種類株式 | 1-3-ロ | |
| 「取締役等のA株式」※※と「取締役等以外のA株式」の区別 | 取締役等の特定株式・取締役等の特定株式以外の特定株式 | 1-3-ハ | |
| 「取締役等以外のA株式」の場合、新株予約権の行使日 | 〇年〇月〇日 | 1-3-二 | |
| 取得した株式に係る事項 | 取得日 | 〇年〇月〇日 | 1-4-イ |
| 取得の事由 | 株式分割・併合・無償割当て・合併・分割型分割・株式分配・株式交換・株式移転・取得事由の発生・取得決議・譲渡・解約・承継・終了等 | 1-4-ロ | |
| 取得した株式の数 | 〇株 | 1-4-ハ | |
| 取得した株式の1株あたりの権利行使価額 | 〇円 | 1-4-二 | |
| 譲渡した株式に関する事項 | 譲渡した日 | 〇年〇月〇日 | 1-5-イ |
| 譲渡の事由 | 譲渡・承継等 | 1-5-ロ | |
| 譲渡した株数 | 〇株 | 1-5-ハ | |
| 1株当たりの譲渡価格 | 〇円 | 1-5-二 | |
| 区分管理帳簿を交付した時の株式数 | 〇株 | 1-6 | |
区分管理帳簿を電磁的記録で作成した場合の保存方法
区分管理帳簿の交付
会社は、次のようなとき、区分管理帳簿の写しを交付しなければいけません(令和6年経済産業省告示第69号第2条)
- 税制適格ストックオプションの権利者が権利行使時
- 株式の譲渡時
表2 「区分管理帳簿」の記載内容に記載しておりますが、区分管理帳簿を交付した時の株式数を記載する必要があります。
株主情報の変更を収集する
税制適格ストックオプションの権利行使をして株式取得した人に関し、次のような内容に変更があれば、情報収集しなければいけません(租税特別措置法施行規則第十一条の三3項2号)。
- 氏名、住所
- マイナンバー
- 死亡した場合、死亡日
- 国外転出した場合、国外転出をした日
事務4:株式を譲渡する
税制適格ストックオプションの優遇措置の適用を受けるためには、租税特別措置法施行令19条の3第9項3号にもとづき
- 金融商品取引業者等への売委託
- 法人に対する譲渡
に限定されます。
したがいまして、金融商品取引業者等へ売委託によらないまま個人へ譲渡してしまうと、税制適格ストックオプションの優遇措置の適用を受けることができなくなるので注意が必要です。
株式を譲渡する人が「税制適格ストックオプションの権利行使により交付された株式(A)」と「税制適格ストックオプションの権利行使により交付された株式以外の株式(B)」を保有していた場合、「(A)と(B)のどちらを何株譲渡するのか?」を明確にしたうえで株式の譲渡手続きを進めてください。
上述しましたが、区分管理帳簿の写しを交付しましょう(令和6年経済産業省告示第69号第2条)
また、売買したときの売買契約書(写し)を徴求し、保管管理しましょう(租税特別措置法施行規則第11条の3 4項8号)。
事務5:「特定株式等の異動状況に関する調書」を提出する
発行会社は、1月31日までに「特定株式等の異動状況に関する調書(こちらになります)」を管轄税務署に提出することになります。
この調書を端的に説明すると、誰がいつどれだけのストックオプションを行使し、いつどれだけ株式売却したという流れを税務署に届ける調書になります。
この調書にはマイナンバーの記載が必要になることから、情報漏洩や記入者の制限に関して、配慮が必要になります。
なお、ストックオプションの発行時には、「特定新株予約権の付与に関する調書(こちらになります)」の提出が必要になるので、念のため確認しておきましょう。
証券会社は、12月末締めで1月末までに提出しています。
まとめ
非上場会社で税制適格ストックオプションの権利行使があった場合の株式事務について、紹介させていただきました。
このブログ作成時点では、経済産業省告示第69条の原文を経済産業省のホームページから検索できず、官報を探し出すしかできませんでした。この株式事務はスタートアップ企業が行う可能性が高いので、誰にでも検索しやすいようにしていただきたいです。
私の見解では、このアウトソーシングサービスをする税理士等の専門家がいればなぁと考えますが、いかがでしょうか?
私が運営しているオンラインサロン「シンIPO AtoZ」は、こんな泥臭い実務についても話しています。ぜひご参加ください!