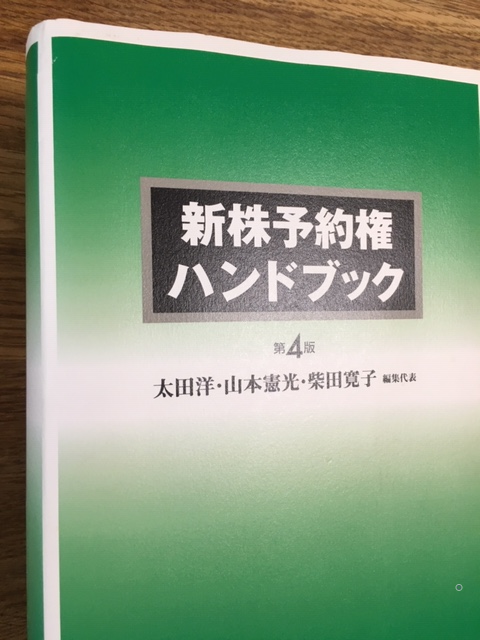非上場会社がIPOを目指す過程におきまして、ストックオプションや新株予約権を発行するケースは多々あります。
ストックオプションは、会社が役職員へ直接、新株予約権を割当てするインセンティブプランです。
2020年に上場した会社の中で、財産保全会社を活用したユニークなインセンティブプランを採用した会社(以下では、「A社」といいます)がありました。
ここでは、IPOを目指す会社にとって、特に会社を設立したばかりのスタートアップ会社の参考となる資本政策の事例をご紹介させていただきます。
譲渡制限のない新株予約権を発行し、財産保全会社へ割当て
IPOを目指すベンチャー企業の多くは、ストックオプションを中心として、新株予約権を利用した資本政策を採用しています。
なお、ストックオプションと新株予約権については、こちらで説明しています。ご参考ください。
新株予約権を発行する場合、ほとんどの新株予約権には、譲渡制限を付けるという設計を用いています。
A社は、譲渡制限を付していない新株予約権を発行しました。
そして、A社が行った資本政策について、ざっくり説明すると次のようになります。
- 創業まもなく、A社は、譲渡制限のない第1回新株予約権を発行。割当対象者は、社長の財産保全会社。
- 上場承認を受ける2か月前(東証による上場審査中)に財産保全会社から、役職員へインセンティブ付与を目的とし、無償で贈与。
ストックオプションとは、会社が役職員へ新株予約権を割当てするインセンティブプランです。
A社の資本政策は、一旦、社長の財産保全会社を経由して、役職員へ新株予約権を割り当てるというインセンティブプランを採用しました。
A社の資本政策には、ストックオプションと比べて次のようなメリットがあると考えられます。
ストックオプションの場合、発行する際に割当対象者と割当個数を決めなければいけません。そのため、ストックオプションの発行時に会社に在籍している役職員にしか割当できません。
割当対象者の中に退職者が出た場合、ストックオプションは無駄に終わってしまいます。また将来に採用する人材のためにストックオプションの割当は、原則出来ません。
A社の場合は、一旦、社長の財産保全会社が新株予約権をプールさせて、上場の達成目途の可能性が高まったタイミングで新株予約権の割当対象者と割当個数を決めるという形になっています。
つまりA社の資本政策は、ストックオプションよりも、上場達成貢献者や上場後の業績貢献に期待する人に対して、手厚く無駄なく効率的に新株予約権を割り当てすることが可能といえます。
IPOを目指す会社は、通常、年々事業拡大をし、その拡大に伴って、株式の時価も高まってきます。
ストックオプションの権利行使価額は、株式の時価と完全にリンクしており、株価が上がると、権利行使価額も高く設定せざるを得ない事態になります。
権利行使価額が高くなればなるほど、キャピタルゲインが小さくなる、つまりストックオプションとしての魅力が低くなってしまうという問題点があります。
A社の場合は、創業間もない時期で権利行使価額が安価に設定できる時期に発行した新株予約権、つまりキャピタルゲインが大きく、魅力的な新株予約権を譲渡出来ることが期待できます。
A社の場合、必ずしも譲渡制限を設けていても、結果的に同じ効果を得ることが出来たと思われますが、役職員へ臨機応変に贈与が可能にするために、譲渡制限をあえて設けない新株予約権を発行していたと推測します。
A社の社名は、オンラインサロンメンバー限定で公開します。「【IPO事例-26】を教えてほしい」とお気軽にお問い合わせください。

譲渡制限のない新株予約権を発行した場合の留意点
会社法上では、譲渡制限のない新株予約権を発行することは問題ありません。
ただし、ブログの中の人が調査した限りでは、税務上で明確化されていないように思われ、顧問税理士への相談は必須です。
ブログの中の人は、A社が採用した資本政策の場合、「新株予約権の贈与時」「新株予約権の権利行使時」「株式の売却時」にそれぞれ納税義務が発生すると考えています。
また、ブログの中の人の考えでは、A社が行った資本政策の場合は、上場承認までに解消、つまり上場承認までに新株予約権の贈与を完了させる要請が上場審査において出てくると思っています。

まとめ
「一般的なストックオプション」と「A社が採用した資本政策」のメリットデメリットは、次のようになると考えられます。
| 一般的なストックオプション | A社が採用した資本政策 | |
|---|---|---|
| 割当対象者や割当数を”後決め”出来る | 出来ない | 出来る |
| 安価な権利行使価額の新株予約権を割当てできる | 不利 | 有利 |
| トータルコスト・導入時の手間 | 有利 | 有利 |
| 税務面のシンプルさ | 有利 | 不利 |
ブログの中の人は、3つのスキームの中で「時価発行新株予約権信託」が最も優れモノだと考えていますが、何せ導入コストと導入時の手間がその他よりも高いことがデメリットにあります。
特に資金が乏しいIPOのアーリーステージにあるベンチャー企業、または設立したばかりのスタートアップ企業は、「時価発行新株予約権信託」よりも「A社が採用した資本政策」の方が検討に値する資本政策の事例であると考えています。
A社の社名はオンラインサロンメンバー限定で公開します。お気軽にお問い合わせください。