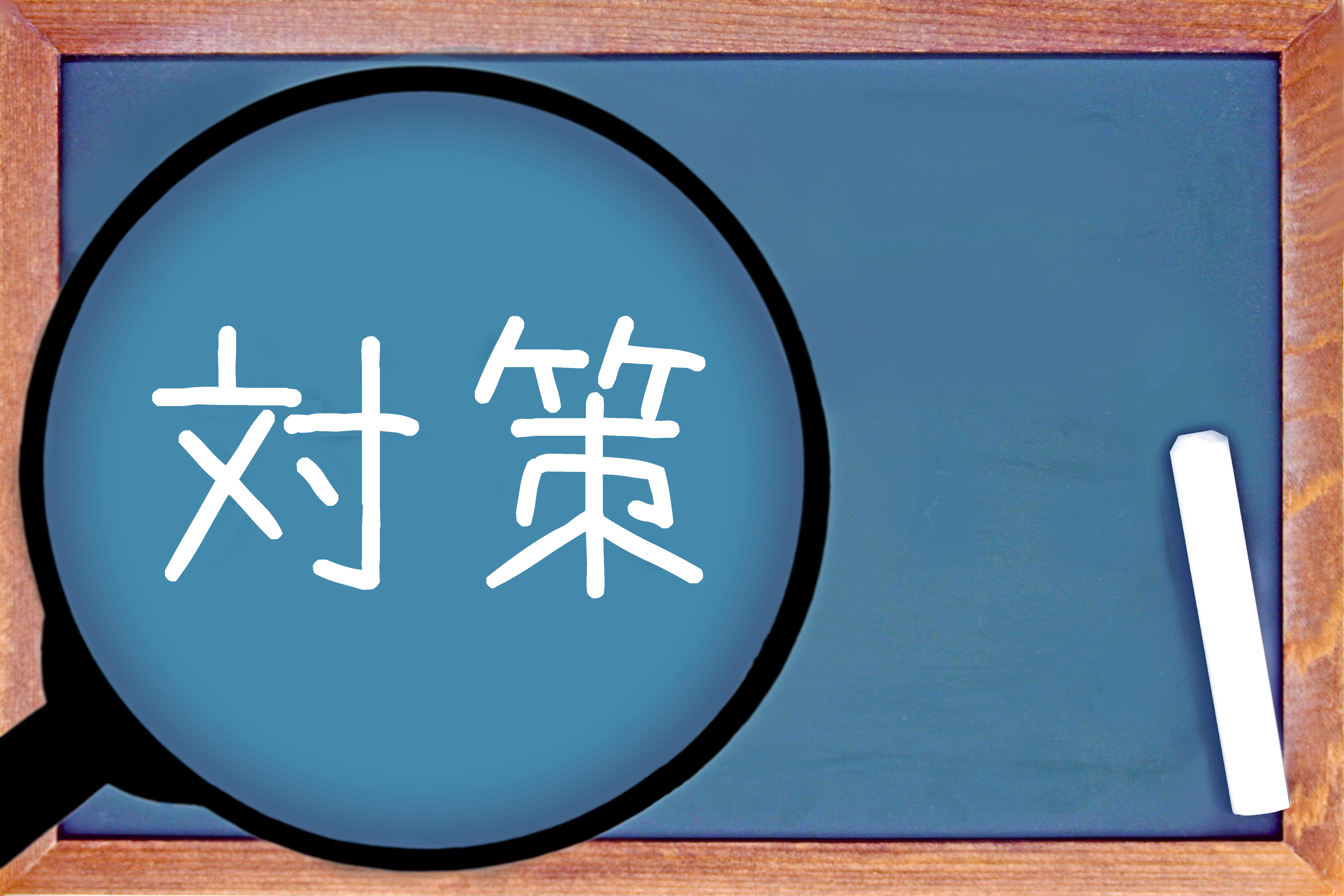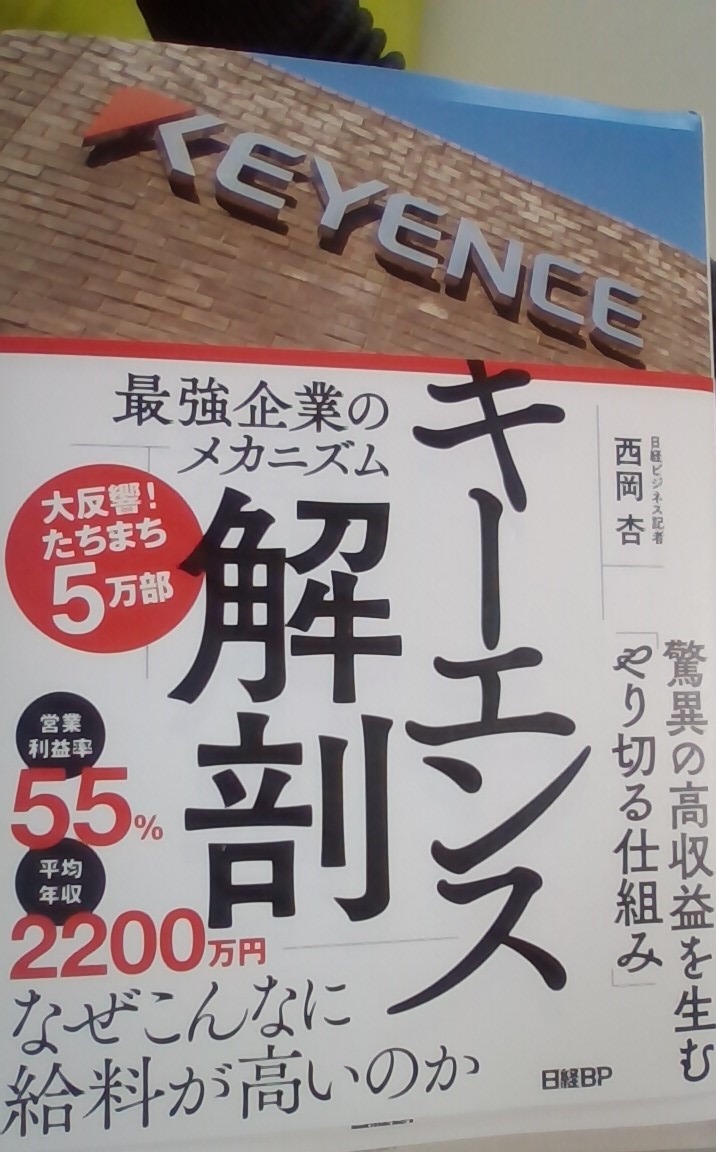上場を支援する人の中には、次のような人がいます。
- コンサルタント
- 顧問
- 社外取締役
ブログの中の人は、どれも経験がありまして、現在は社外取締役をしています(このブログを立ち上げたことに伴い、コンサルタントと顧問を止めました)。
私が社外取締役を勤めている会社の社長から「年配者は顧問で、若い人はコンサルタント」という一言がありました。
きっと、顧問とコンサルタントの違いを知らない方は、意外と少なくないのではないでしょうか?
ここでは、顧問とコンサル、また社外取締役がどのような点で異なるのかということを簡単に説明させていただきます。
なお、意見・見解については、あくまでもブログの中の人の個人的な意見・見解であることにご留意くださいますようお願いします。
コンサルタント
まず、コンサルタントについて説明させていただきます。
コンサルタントとのコンサルティング契約
コンサルタントは、コンサルティング契約を締結することにより、役務が開始されます。
コンサルティング契約は、法人と法人の間、もしくは法人と個人の間で交わされます。
そのコンサルティング契約には、「内部統制を・・・・」「社内規程を・・・」「内部監査体制を・・・」というような、具体的な役務提供が定められていることが一般的であり、つまりその役務提供内容が終了すれば、ひとまず契約は終了になります。
つまり、IPOのコンサル業務は、IPOを目指す会社とIPOコンサルの間で交わす契約書で、IPOコンサルの役務提供内容、また役務に対する成果物、または成果レベルを一定以上明確化させてから、動き出すということになります。
簡単にまとめますと、次のようになります
- IPOコンサルの役務内容がプロジェクト単位になっており、明確である
- コンサルの役務終了に伴い、コンサル契約は終了する
したがいまして、IPOのコンサル契約は、IPOを目指す会社にとっての課題を明確化してから、締結することになります。
上場審査や法規則上の留意点
上場申請書類においては、コンサルティング契約について次のような規則があります。
- プライム市場、スタンダード市場
- 直直前事業年度及び申請事業年度において、経営指導等を目的としたコンサルティング契約・顧問契約等(専門職者の非常勤雇用等を含みます。)を締結していた場合(現在、締結しているものも含みます。)には、その具体的な内容(契約締結年月、契約の相手先、契約の名称、契約の概要(期間、報酬額、成果等))を記載してください。
- グロース市場
- コンサルティング契約の締結について「新規上場申請者に係る各種説明資料」に記載
期待する能力
上場準備においては、会社の課題を発掘し、その課題を乗り越えるということを繰り返すことになります。
上場コンサルに期待する能力や役割とは、課題を発掘する能力や役割ではなく、その課題を乗り越えようとする能力の方になります。
課題の発掘は、基本的に監査法人や主幹事証券会社、または証券取引所が行うためです。
逆に申し上げますと、IPOコンサルタントの中には、その会社の課題や問題を発掘できない人、またはあえて指摘しない人が存在します。
時々、「うちの会社は、あのIPOコンサルと長く付き合っているが、そんな問題を指摘してくれなかった」と仰る方がいらっしゃいます。
しかし、それが普通であり、珍しいことではありません。

顧問
上場を目指す会社にあたっては、会計士、弁護士、社労士、税理士、司法書士などの専門家と顧問契約を交わす会社が多く存在します。
ここでは顧問について簡単に説明させていただきます。
IPOの顧問契約
顧問とは、顧問契約を締結することになります。
顧問契約は、法人と法人の間、もしくは法人と個人の間で交わされます。
顧問契約は、コンサルティング契約とは異なり、具体的な役務内容が定められていないことが通常です。
コンサルティング契約は、プロジェクトに対する具体的成果に対して報酬を支払うことに対し、顧問契約は、顧問に対する拘束時間へ報酬を支払うというイメージになります。
簡単にまとめますと、次のようになります。
- 契約段階で役務提供内容が具体的ではない。
- 顧問する期間の満了に伴い、顧問契約は終了する(満了後、自動更新するケースが多くあります)
上場審査や法規則上の留意点
顧問の対象者や顧問契約内容次第で、役員に準ずる者として定義されれば、関連当事者に該当することになるなど、ややこしくなります。
顧問の中には、名誉職的に使われているケースがあり、引受審査に入る際に、きっと締結している全ての顧問契約の写しの提出を求められ、調査されるはずです。
関連当事者の範囲にならなくとも、コンサルタントと同様、Ⅱの部等で契約内容について、記載を求められます。
また、社長等の役員が退任後、顧問に就任しているケースがあります。その場合、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」にて報酬等を開示することになります。
期待する能力
上場準備をするにあたっては、課題を発掘し、その課題を乗り越えるということを繰り返すことになります。
IPOコンサルは上場準備会社の実務担当者と一緒になって、課題を乗り越えるために現場で汗をかく人である一方、顧問は一般的に現場で汗のかく人ではありません。
上場準備会社にとって、IPOコンサルは求める成果に対して報酬を支払っている一方、顧問に対しては一般的に拘束時間に報酬を支払っているため、顧問に現場で汗をかかせるような事を要求してしまうと顧問契約の範疇を超えてしまうことになりやすくなるためです。
顧問は、課題を乗り越えなければいけないときに、効率的な課題の乗り越え方を教えてくれる人のイメージが中心になります。
社外取締役
上場コンサルや顧問は、上場を目指すにあたって、契約をしなければいけないという義務がありませんが、社外取締役の設置は義務になります。
社外取締役については、↓で説明しています。
社外取締役の契約
社外取締役が選任されると会社と委任契約を締結します。
顧問やコンサルと違い、法人と法人で契約締結が出来ません。
契約期間は、定款で定められている取締役の任期までであり、その任期が到達すれば、一旦終了です。
コンサルに対しては期待する成果へ報酬を支払、顧問に対しては拘束時間へ報酬を支払うイメージです。
それらと比較すると、社外取締役に対しては、会社法上の責任へ報酬を支払うというイメージになります。
上場審査や法規則上の留意点
メチャクチャあります。
このブログIPOAtoZの文字検索欄で社外取締役を入力すれば、いっぱい出てきますので、ぜひご参考下さい。
法規則には入っていませんが、顧問やコンサルタントとは違い、業界のプロを社外取締役に就任させることは、リスクが高くなります。
業界のプロとは、競合企業相手にも仕事をしている人です。
会社は、顧問や上場コンサルに対して、一定レベルの情報遮断が可能ですが、社外取締役に対する情報遮断は難しくなるはずです。
業界のプロは、社外取締役退任後も業界のプロとして生き続けるわけですからね。
期待する能力
上場を目指す会社は、コンサル契約や顧問契約を締結する際、一定以上の専門性を求め、専門知識を重要視しますが、社外取締役には、専門知識より、正義感や総合的な経営判断能力が重要視されます。
コンサルタントや顧問は銭ゲバであっても問題ありませんが、「俺にストックオプションを出せ!」「報酬が安すぎる!」と不満を言うような社外取締役は問題になるでしょう。
また、社外取締役は、取締役会と株主総会などの重要会議に出席しなければいけません。
上場コンサルや顧問は、必要なときにスケジュールを調整することができますが、社外取締役の場合は、そういうわけにはいきません。
つまり上場コンサルや顧問は、案件や顧客を無限大に抱えることが可能ですが、案件や顧客を多く抱えた人を社外取締役に選任させるのは難しいです。
↓に関連する記事があります。ご参考下さい。
まとめ
以上をまとめると次のようになります。
表 「コンサルタント」「顧問」「社外取締役」の違い
| コンサルタント | 顧問 | 社外取締役 | |
|---|---|---|---|
| 契約内容 | 役務提供に対する成果物が具体的 | 役務提供の範囲が定められている程度 | 会社経営の監督を果たすための契約内容 |
| 契約期間 | 一般的には、プロジェクトが終了するまで | 一般的には、契約期間を定めている | 定款で定められた期間 |
| 報酬 | 成果物の質や量へ報酬を支払う | 顧問の拘束時間へ報酬を支払う | 責任の大きさへ報酬を支払う |
| 求められる主な能力・資質 | 課題克服力 | 専門性 | 正義感、総合的な経営判断能力 |
| 上場審査に対する留意事項 | コンサルタント任せであれば、問題視 | 名誉職のような場合、問題視 | 兼業が多い場合、問題視 |
例えば、規程の作成プロセスに関して、コンサルタントと顧問、社外取締役の役割をイメージすることにすると、次のようになります。
- コンサルタント:規程のひな型・たたき台の作成提出、完成版の策定や規程内容を社内に定着させるための支援
- 顧問:規程の内容についてのセカンドオピニオン、法律面や会計面などとの適合性確認
- 社外取締役:規程の承認
というようなイメージになります。
なお、このブログのサポーターとなっていただいている上場コンサルタントや顧問の一覧は、こちらにあります。
IPOAtoZでは、最新情報をTwitterで紹介しています。ぜひフォローをお願いします。