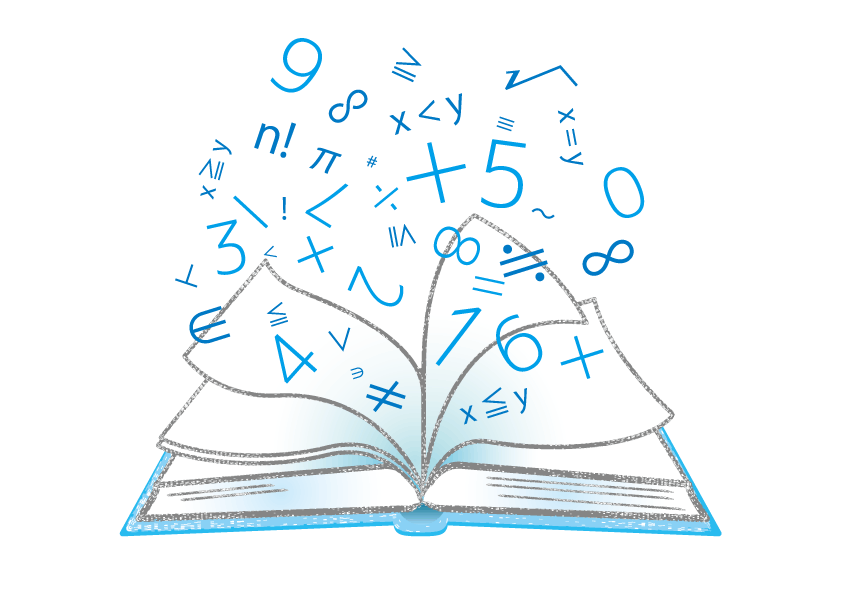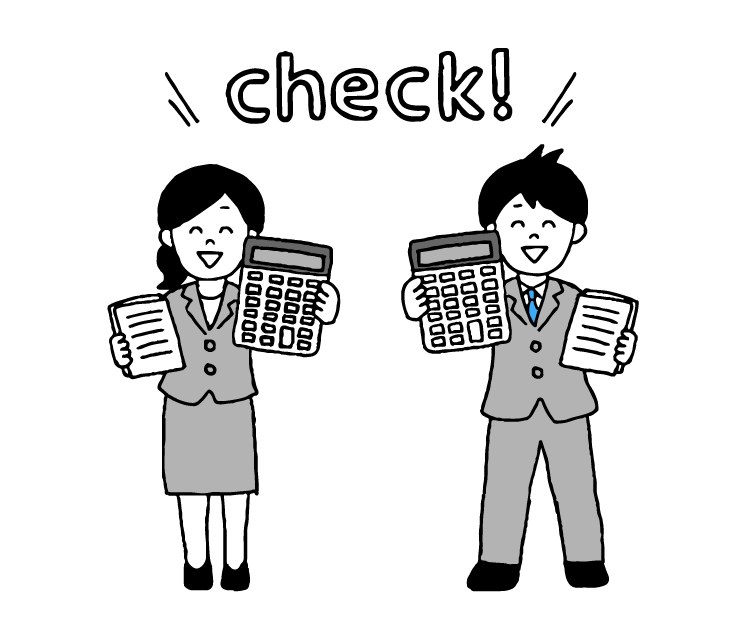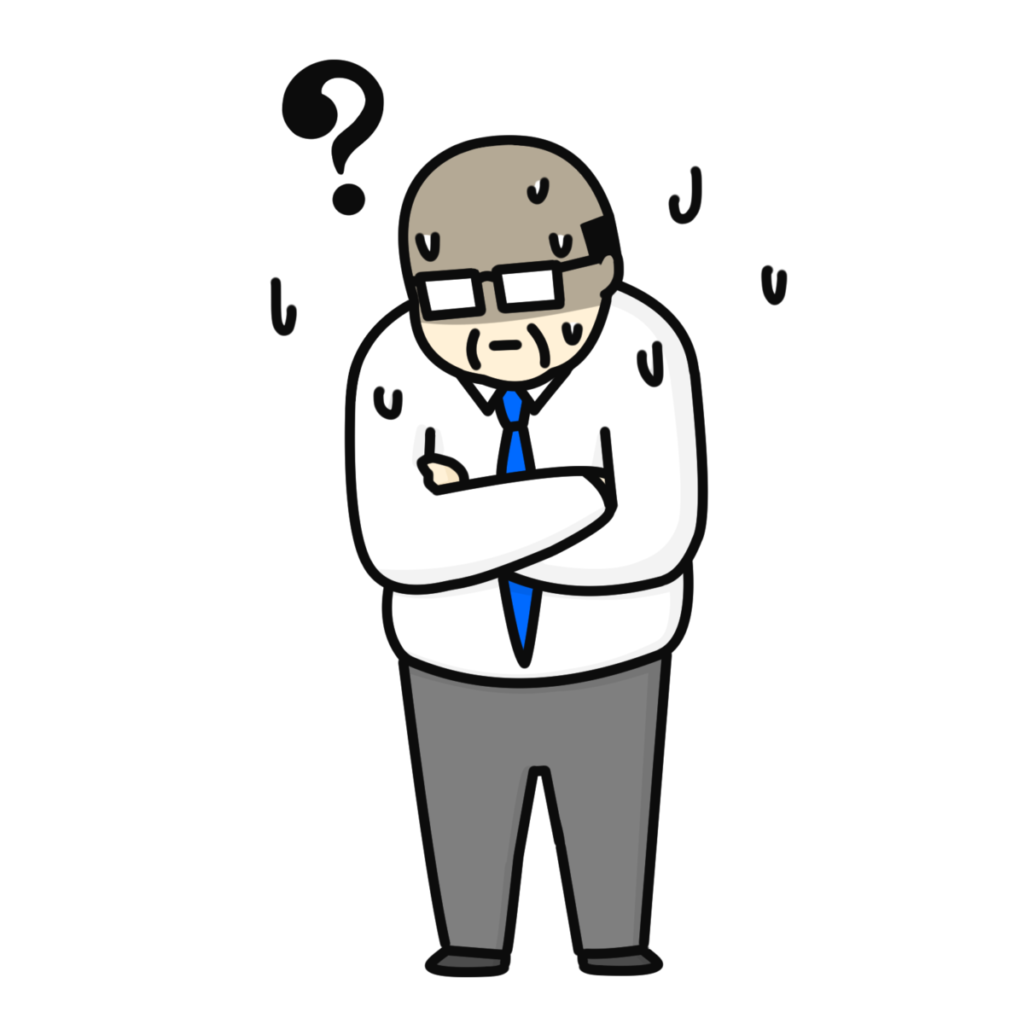
「おばあちゃん ええ儲け話ありまっせぇ。この会社、近々、上場するらしいですわぁ。上場する前にその株を持ってたら、すごく儲かりまっせぇぇ」
みなさんご存知の投資詐欺です。
IPOを目指す会社の株主、またはその周辺にこんな人がいれば大変です。
もし株主がこのような事件を起こしてしまえば、間違いなくIPO準備は中断です。
しかし投資詐欺に巻き込まれた会社がIPOを達成した事例がありましたので紹介させていただきます。
未公開株の投資詐欺
このブログをご覧の方々であれば、ご存知かと思いますが、非上場株の投資詐欺事件は、毎年のようにあるようです。
警察庁 「生活経済事犯」によると、未公開株の投資詐欺は、「利殖勧誘事犯」のカテゴリーにあるようでして、表1のようになっています。
表1 利殖勧誘事犯の検挙状況(出所:警察庁 「生活経済事犯」より)
| 令和元年 | 令和2年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 相談件数 | 検挙事件数 | 検挙人員 | 相談件数 | 検挙事件数 | 検挙人員 |
| 1,560件 | 41事件 | 176人 | 1,806件 | 38事件 | 130人 |
令和2年にあった38件の検挙事件数の内、7.9%(つまり、3件と思われます)が未公開株での検挙事件となっています。
このような詐欺に騙されるな!と関係各所は次のようなサイトで呼びかけています。
投資詐欺があったら、どうなるのか
IPO準備段階で株主の一部が詐欺行為をおこなった事実が判明した段階で、間違いなくIPO準備はストップすることになるだろうと考えます。
まず経営者は、会社法で認められている「特別支配株主の株式売渡請求(会社法第179条)」などを利用して、当該株主の排除することをしなければならず、その株主が株主名簿の中に存在する間は、きっとIPO準備を再開できないと思います。
さらに詐欺行為に加担した株主が反社会的勢力との繋がりがあることが判明したとなると、その株主を排除したとしても、速やかに主幹事証券会社が現れるとは考えられません。IPO準備のストップ期間は、更に長期化するのではと考えます。
また、詐欺にあった人から損害賠償責任の請求が来るような可能性が極めて低くなるまで、IPO準備の再開は難しいかもしれません。

サイバートラストと投資詐欺犯罪
2021年4月15日に東証マザーズへ上場したサイバートラスト株式会社のⅠの部には、次のような記載があります。
旧サイバートラスト㈱の株式について、①同社元役員がその保有する同社の株式を第三者に譲渡した後、これを転得したブローカーが、1998年頃から2010年頃までの間に、同社の株式が上場予定であるとの虚偽の事実を告げて勧誘を行い、同社の株式を個人投資家に高値で譲渡した事例、及び②同社元役員が、第三者と共謀のうえ、2003年12月頃から2008年8月頃までの間に(その一部は同社元役員が同社に在籍していた時期と重なります。)、同社株式について同様の虚偽の事実を告げて同社の株式に投資する投資事業組合への出資の勧誘を行い、その結果個人投資家から金員を詐取した事例を認識しております。しかしながら、前者の事例についてはブローカーが詐欺の主体であり、後者の事例については同社が会社として関与した事実ないし知り得た事情は認められません。したがって、いずれの事例についても同社の関与は認められず、また不法行為に基づく損害賠償責任の消滅時効期間は既に経過しているため、仮に高値で同社株式を取得した個人投資家又は詐取の被害にあわれた個人投資家が、当社に損害賠償を請求したとしても、当社が損害賠償責任を負うことはなく、したがって、当社の財政状態に与える影響はないと考えております。
↑のⅠの部の記載内容について、ググってみますと、「同社元役員」というのは、元社長のようであり、逮捕されたようですね。
サイバートラストの株式管理に関する問題は、投資詐欺だけではありません。
2002年又は2003年頃から2005年にかけて、旧サイバートラスト㈱の当時の大株主であったBaltimore社は旧サイバートラスト㈱の株式を複数回に分けて譲渡し、その65%弱を特定の投資家が取得しております。もっとも、当該投資家がその株式をBaltimore社から直接取得したのか、又は第三者を経由して取得したのかが明らかではなく、結果として当該株式の譲渡に必要であった旧サイバートラスト㈱の取締役会の譲渡承認を欠いていた可能性があります。しかしながら、①当該株式譲渡の無効を主張する可能性のある者は限定されていること、②(株式譲渡の経緯と正確には一致していない可能性はあるものの)当該投資家が株式を取得すること自体についての旧サイバートラスト㈱の取締役会の承認はあること、③当該株式譲渡からは既に相当長期間(約15~17年)が経過しているにもかかわらず当該株式譲渡の無効を主張されたことはないため、仮に当該主張がなされたとしてもこれが認められる可能性は低いこと、④上記のとおり2017年10月1日に当社と旧サイバートラスト㈱との間の吸収合併が行われ、当該吸収合併に関する合併無効の訴えの提訴期間が経過していること、及びその他の諸般の事情を考慮いたしますと、上記の旧サイバートラスト㈱の取締役会の譲渡承認を欠いていた可能性がある株式譲渡について、当社の過去の株主又はその他の者から、その無効が主張されるリスク及び当該主張が認められるリスクは低いと考えており、したがって、当社の株式の帰属が争われるリスクもまた低いと考えております。
取締役会の承認なしで、サイバートラストの株式譲渡が行われたようです。
投資詐欺の防止策
サイバートラストの例を見ると、次のような防止策が考えられます。
株券不発行会社にする
サイバートラストにあった不祥事とは、サイバートラストの株券が会社から無断で譲渡されていたという原因があります。
サイバートラストと同様な事にならないようにするためには、まず株券不発行会社になることだと思います。
もし履歴事項全部証明書の中に「当会社は株券を発行する」というような記載がされていると株券発行会社であるため、この一文を削除する手続きを進めることをおススメします。
この記載があるにも関わらず、実際に株券を発行していない会社(いわゆる「株券不所持会社」)もありますが、株券の偽造リスクなどを考慮しますと、株券不発行会社に移行すべきだと思います。
株券発行会社から不発行会社に移行するためには、株主総会決議を経て、定款変更を行うことになります。
株式譲渡制限会社にする
非上場会社のほとんどは、株式譲渡制限会社ですが、中には公開会社があります。
つまり、公開会社と上場会社は、似て非なる用語です。
違いを簡単に表2に紹介します。
表2 公開会社と上場会社の違い
| 違い | |
|---|---|
| 公開会社 | 一部の株式でも譲渡の制限をつけない会社 |
| 上場会社 | 発行する株式が証券取引所で売買されている会社 |
非上場会社にありながら、公開会社になるメリットはありますが、その反面、最大のデメリットは、未公開株投資詐欺が起きてしまうリスクがあると思います。
株主数を削減する
株主数が多ければ、多いほど株式管理に関する問題が発生するリスクが増加します。
経営陣と人間関係が薄い、行動が不安、
そこで株主数を削減することもひとつの方策です。
株主数の削減は、色々な手段があります。
- 自己株式
- 株式併合
- 役員、または従業員持株会、関係が深い事業会社に譲渡させるなど
まとめ
サイバートラストの業績をみてみますと、本来なら、もっと早期にIPOを実現したのではと思われます。
つまりサイバートラストのⅠの部を見た限り、株式管理で問題が発生して場合、会社が犯罪を犯していなくとも、不法行為に基づく損害賠償責任の消滅時効期間を超過するまでIPOを待たざるをえなくなる可能性がありそうです。
そこで、IPOを目指す会社は、サイバートラストの例を他山の石として考える必要があります。
主幹事証券会社は、IPOの準備支援作業に取り掛かる上で、最初に行う基本動作として、自社株式の管理状況の確認があります。
株券発行会社に対しては、株券の現物確認と株券不所持の申し出を証する書面の整備が求められることになります。
株主数が多い会社は、非常に面倒な作業になります。
まず、株券不発行会社に定款変更する手続きを進めることをおススメします。
IPOAtoZでは、このようなレアなIPO事例を蓄積して情報提供しています。
上場準備作業においては、特に主幹事証券会社との間でトラブルになることがよくありますが、IPO事例を知れば、一気に解決という事があります。
こちらになります。ぜひご参考ください。