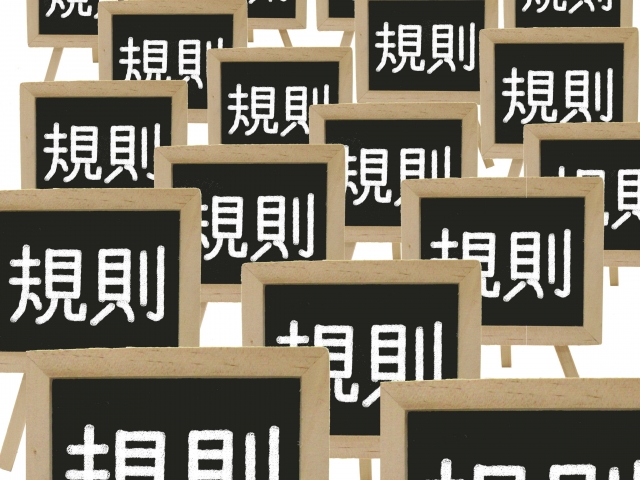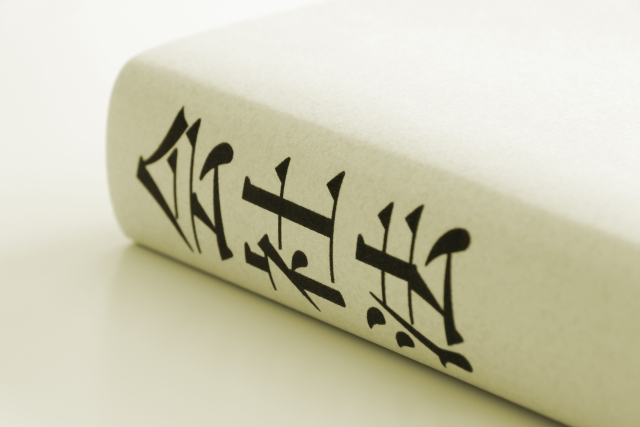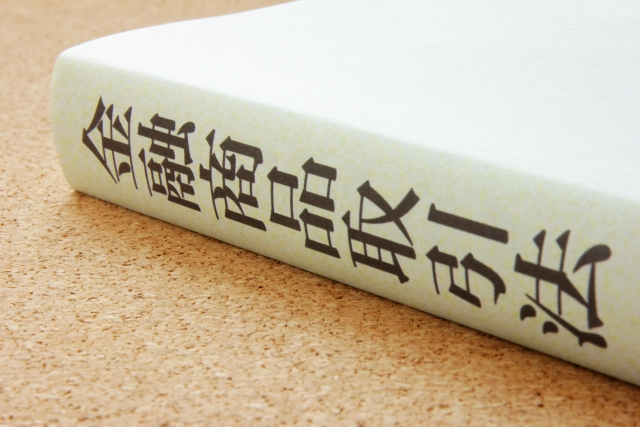
上場すれば、ほとんどの会社が業績予想を開示することになります。
しかし、その業績予想から一定以上の差異が発生した場合、その差異に関する情報が「重要事実」となります。
そして、その差異に関する情報を公表する前にその重要事実を知った人が株式等を売買した場合、または他人に対して利益獲得・損失回避の目的で重要事実を伝達した場合、最悪のケースで逮捕されてしまいます。
簡単ですが↓で説明しています。重要事実については、以下で説明しています。
旬刊商事法務No2321「SHIFT社CFO事件を踏まえた業績予想等の修正に係る実務上の留意点」が上場を目指す会社関係者にとりまして、「業績予想等の修正に係る重要事実」の参考になる内容になるのではないかと思い、取り上げさせていただきます。
内容の詳細につきましては、こちらの「旬刊商事法務」をお買い求め下さい(アフィリエイトではありません。商事法務さん、もしアフィリエイト広告を行っているのであれば、ぜひ宜しくお願い致します!!!)。
SHIFT社CFO事件とは
株式会社SHIFTの役員が広島県で開催された高校時代の友人との飲み会で重要事実である業績予想等の修正を同級生に話し、株式会社SHIFTの株式を保有していた同級生が株式を売却したという疑いがあった事件です。
詳細は、金融庁の平成29年4月11日「株式会社SHIFT役員による重要事実に係る伝達に対する課徴金納付命令の決定について」(こちらになります)をご覧ください。
その役員は、その命令に対し「何でワシが金払わなあかんのじゃぁ!飲み会のとき、わしゃぁ、重要事実なんか知らんけぇのぉ!(広島弁ってこんな感じでよろしいでしょうか?仁義なき戦いをイメージしています。)」と課徴金納付命令を不服として、裁判で争いました。
そして令和4年10月13日に東京高裁で判決が出され、10月28日に判決が確定しました
結果としては、役員側が勝ち、課徴金納付命令が取り消されました。
金融庁の発表は、こちらになります。
また、この事件に関連する日経新聞の記事は、こちらになります。
業績予想等の修正に係る重要事実とは
金融商品取引法第166条2項第3号において、会社の直近の業績予想値と”一定以上の差異”が生じた事を知った人は、差異の内容について公表した後でなければ、当該会社の有価証券等の売買等が出来ないという禁止行為が定められております。
”一定以上の差異”については、以下のような内容になっています。
- 売上高
- 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)で除して得た数値が1.1以上又は0.9以下であること。
- 経常利益
- 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)で除して得た数値が1.3以上又は0.7以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前事業年度の実績値が零の場合はすべてこの基準に該当することとする。)
- かつ、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値と公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額で除して得た数値が5/100以上であること。
- 純利益
- 新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)で除して得た数値が1.3以上又は0.7以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前事業年度の実績値がゼロの場合はすべてこの基準に該当することとする。)
- かつ、新たに算出した予想値又は当事業年度の決算における数値と公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前事業年度の実績値)とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前事業年度の末日における純資産額と資本金の額とのいずれか少なくない金額で除して得た数値が2.5/100以上であること。
業績予想等の修正に係る重要事実について、よく知られているのが、売上10%、利益30%という2つです。
上場準備会社においては、直前期や申請期の売上が予算より10%超、利益が30%超ズレそうになれば、証券会社の公開引受部門担当者がおそらく「予算を修正しないのですか?」と言うはずです。
しかし、それ以外に主に以下のような点も留意すべきことになります。
業績予想等を出していない会社でも重要事実に無関係ではない
ほとんどの上場会社は、決算短信で業績予想等を出していますが、出していない会社もあります。
例えば、野村證券の親会社の野村ホールディングス、大和証券グループ本社、三菱UFJフィナンシャル・グループ等が業績予想等を出していません。
そうなれば「業績予想を修正する場合、重要事実になる可能性があるのだから、そもそも業績予想を出さなきゃいいじゃん!」という発想に走ってしまいそうですが、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第51条第1号から第3号を読むと、業績予想等を出していない会社の場合は、業績予想の代わりに前事業年度の業績を基準とされている事がわかります。
したがいまして、業績予想を出さないことがリスクヘッジ策に結び付かない事になります、
BSも業績予想等に係る重要事実に関連している
利益が予想から30%超ズレると判明した場合、重要事実が発生すると思っている方が多くいらっしゃいます。
しかし、その利益とは、経常利益または当期純利益の事でありまして、売上総利益や営業利益は関係ないこと、そして、その利益が30%超ズレただけで、重要事実に直結するのではないという点を知っておきましょう。
純資産額と資本金の額と比較して、一定以上の水準でなければ、重要事実にならないという点も注意しましょう。
業績予想等の修正に係る重要事実が発生する時点
この裁判での、第1審の判決文(こちらになります)には、以下のような一文があります。
金商法167条の2第1項等の上記⑵の趣旨に鑑みると,上場会社等において増減率が基準値以上となる純利益の予想値を「新たに算出した」(同法166条2項3号)といえるためには,当該予想値に係る業績予想修正につき当該上場会社等における正式な決定(本件では,本件書面決議による本件業績予想修正の承認)を必ず経なければならないものではなく,当該上場会社等における実質的な意思決定がされれば足りるというべきである。
(出所:平成29年(行ウ)第192号 課徴金納付命令取消等請求事件口頭弁論終結日 令和3年7月20日判決文より)
この判決文によると「新たに算出した時点」が「実質的な意思決定時点」になるものと解釈されます。
そこでブログの中の人が「岡田社長が経営する阪神タイガース株式会社」をイメージし、阪神タイガース株式会社が業績予想を変更したプロセスを↓に示します
- 「ほんまに今期の業績がアレやなぁ。予想の変更せなあかんなぁ。お~ん」と岡田社長がつぶやく
- 「ほんまでんなぁ」と他役員が同意する
- 岡田社長が青柳取締役兼管理部長に「業績がアレやから、予想をアレせなあかんわ。頼むわ。お~ん」と青柳取締役兼管理部長に本年度の着地予想の再作成を指示し、青柳取締役兼管理部長が了承する
- 青柳取締役兼管理部長は、部下の湯浅経理課長に「予想を再作成して」と指示する
- 湯浅経理課長は、米国マイアミ出張があり、ウキウキ気分なので、新人の森下社員に丸投げする
- 中央大学を出た期待の新人である優秀な森下社員は、マジメに本年度予想の再作成案を完成させる。そして「面接の時、儲かっていると言われていたのに、ウソやったわ。読売ジャイアンツ株式会社に入社した方がよかったわ」とつぶやく
- 森下社員は予想の再作成案を米国マイアミから帰国した湯浅経理課長に見せる
- 湯浅経理課長は修正予想案を確認し「俺のフォークボール並みに業績落ちるなぁ」とつぶやく
- 湯浅経理課長は、青柳取締役兼部長に再作成した修正予想案を提出する
- 青柳取締役兼管理部長は「あ~やっぱり、売上が10%超、当初予想より落ち込むんやなぁ」とつぶやき、岡田社長に修正予想案を見せる
- 岡田社長「お~ん。やっぱりアレやなぁ。アレがアレでアレになったわ。営業に新しい外人呼ばなあかんなぁ。」と言い出し、取締役会に修正予想案を付議する事を決める
- 取締役会で予想の変更を決議する
阪神タイガース株式会社の場合、「新たに算出された時点」が「12.取締役会で予想の変更を決議する」の時点であるとは限らず、1.~11のいつの時点なのかが議論になります。
旬刊商事法務No2321の記事を読むと、「新たに算出された時点」の答えは「8」になるようです。つまり、予想を作成する責任部署である湯浅経理課長が修正予想案を確認した時点になります。
イメージとしては、
8の時点で、阪神タイガース株式会社において、湯浅経理課長と森下社員が初めてインサイダー情報保有者となり、9の時点で、青柳取締役兼管理部長に拡がって。。。という事になります。
ちなみにブログの中の人は、旬刊商事法務No2321の記事を読む前まで知りませんでした。
旬刊商事法務No2321「SHIFT社CFO事件を踏まえた業績予想等の修正に係る実務上の留意点」
この記事には、主に以下のような事が書かれています。
- 「新たに算出された時点」とはどのような時点であるか?
- 実務上の留意点
- 証券取引等監視委員会による質問調査等への対応
- 業績値の確定手続の策定
- 取締役会議議事録等の社内資料への記録化
- 業績予想等の修正に係る情報管理
- 社内規程の整備等
予算の修正は、どの会社でも起こりうる場面です。
SHIFT社CFO事件を題材にして、業績予想等の修正に関してどのような実務上の取り組みをすべきなのかを提案している記事内容になります。
記事の内容については、当該記事の著作権を考慮し、これ以上の紹介を控えさせていただきます。
まとめ
業績予想等の修正に係る重要事実について、SHIFT社CFO事件を参考にして紹介させていただきました。
上場準備段階で、予算管理規程を作成します。
その中には、予算の修正に関する条文が存在すると思われます。
予算の修正に関する条文には、予算修正のプロセスが記載されていると思われますが、ほとんどの会社の予算管理規程では、どの時点が「新たに算出された時点」となり得るのかという意識が入った条文になっていないと思われます。
SHIFT社CFO事件での判決文を少し意識して、皆様の会社が予算を修正する際、「新たに算出された時点は、当社にとって、どのタイミングなのか?」をご検討されてはいかがでしょうか?
なお、「「新たに算出された時点」とはどのような時点であるか?」につきまして、旬刊商事法務の記事では、三國谷勝範「インサイダー取引規制詳解(資本市場研究会)」の101頁~102頁を引用してサラっとだけ記載されています。したがいまして、旬刊商事法務の記事よりも、その資料の方に詳細が記載されていると思われます。
また金商法に関する判決でIPOを目指す会社にとりましても注目すべき判決がありましたら、積極的に取り上げる予定です。
↓もご参考ください。
IPO AtoZでは、Twitterで上場準備に関する情報を発信しています。
ぜひフォローをお願いします。