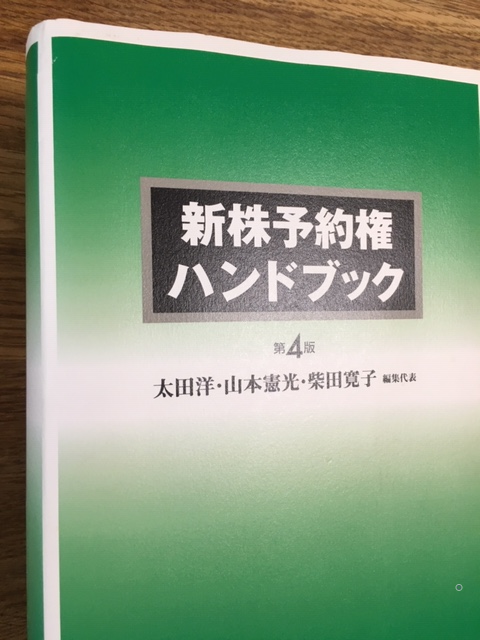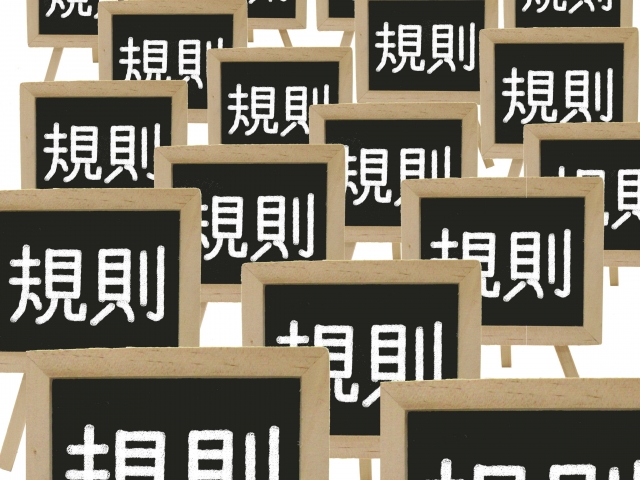2019年と2020年に東証へIPO(AIM市場除く)を達成した会社(174社)の内、ストックオプションを発行した件数は、156社ありました。
そして割当対象者は、表1のような件数になっています。
表1 2019年と2020年に東証へIPOを達成した会社のストックオプション割当対象者
| 順位 | 割当対象者 | 社数 |
|---|---|---|
| 1位 | 取締役への割当 | 149社 |
| 2位 | 従業員への割当 | 148社 |
| 3位 | 監査役または監査等委員への割当 | 57社 |
| 4位 | 社外協力者または取引先への割当 | 50社 |
| 5位 | 子会社の従業員への割当 | 34社 |
| 6位 | 子会社の取締役への割当 | 31社 |
| 7位 | 資産管理会社への割当 | 4社 |
| 8位 | 親会社取締役または親会社従業員への割当 | 1社 |
| 9位 | 顧問への割当 | 1社 |
| 10位 | 入社予定者への割当 | 1社 |
(出所:IPOAtoZ調べ)
ストックオプションの発行を決めた際、誰にどれくらい割当対象者と配分を決めることになり、頭を悩ますことになります。
ここでは、割当対象者別の主な論点について説明させていただきます。
ストックオプション、新株予約権につきましては、こちらで説明していますので、ご参考ください。
※正確に言いますと、「親会社取締役」「親会社従業員」「社外協力者・取引先」「資産管理会社」「入社予定者」に割当てする場合、ストックオプションとは呼びません。
取締役・従業員へストックオプションを割当する場合の論点
ほとんどのケースは、大きな議論が生じませんが、次のような議論が発展するケースがあります。
オーナー社長へのストックオプション
コーポレートガバナンスコードには次のような原則が存在します。
買収防衛の効果をもたらすことを企図してとられる方策は、経営陣・取締役会の保身を目的とするものであってはならない。その導入・運用については、取締役会・監査役は、株主に対する受託者責任を全うする観点から、その必要性・合理性をしっかりと検討し、適正な手続を確保するとともに、株主に十分な説明を行うべきである。
すでに議決権の過半数を大幅に超えるような株式を保有しているオーナー社長へストックオプションを割当てする場合、議論になります。
コーポレートガバナンスコードにあるように保身的な理由によって、買収リスクを過度に恐れる会社経営者は、IPOを止めるべきという考えが強くあります。
敵対買収が起きれば、社会に何等かのリスクが発生する可能性があるというようなことをアピールできるようにしなければいけないと考えられます。
IPO準備段階でオーナー社長へストックオプションを割当てしてしまった場合、IPO直前に権利行使をしてもらうという事例がよくあります。
オーナー社長の親族は?
創業以来、節税対策として、オーナー親族を従業員として雇っている会社がよくあります。
その中には、ほとんど勤務せず、名目だけの従業員となっているケースも存在します。
オーナー社長が経営している会社の場合、オーナー社長の親族に付与する場合に議論が発展します。
IPOを会社の利益より、オーナー親族の利益を優先するような傾向にないかどうかの確認がされます。
特に、次のようなストックオプションは、相当議論に発展すると思います。
またオーナー(発行済株式総数の3分の1超を有する者)およびオーナー親族は、税制適格ストックオプションの適用対象者から除外されます。
割当の配分は、平等?
審査では、配分ルールについて問われるケースが多々あります。
ストックオプションの配分については、「役職」または「勤務年数」で階層化するか、または全従業員で平等に割当てるというように、第三者からストックオプションの配分について公平性を確認できる場合は問題となるようなことはありませんが、配分ルールが明確ではなく、かつ社長個人に密接な人への配分が厚くなっているような場合、問題に発展します。
ブログの中の人が担当した会社では、社長の愛人にストックオプションを手厚く割当したことがありました(マジです)。
監査役・監査等委員へストックオプションを割当する場合の論点
10年ほど前は、「監査役へストックオプションを付与しても問題ないか?」と東証へ相談すればNOという返事でしたが、近年、監査役へストックオプションを割当てするケースは多くなってきています。
ISSやグラスルイス等、議決権行使助言会社や機関投資家は、監査役へストックオプションを付与することに対し、一律的に反対でしたが、今は条件や内容次第で反対しないような意見が多くなっています(現在もNOという意見を持っている機関投資家もいます)。
また、監査役へストックオプションを割当てしようとする場合、監査役は税制適格ストックオプションの適用対象者ではない(監査等委員の取締役は、適用対象者)ことが論点になるのですが、その他にも、次のような論点があります。
割当数が多すぎない?
監査役・監査等委員は、少数株主を代表して、取締役をウォッチするという重要な役割を担っています。つまり、監査役・監査等委員は、取締役に対して、第三者目線でギャーギャー言う立場になるので、取締役にとって、目障りな存在になります。
監査役・監査等委員へ多くのストックオプションを割当てすると、「ストックオプションが口止め料、もしくは賄賂的なものにあたるのでは?」と、監査役・監査等委員がコーポレートガバナンスにおいて有効に機能するのか疑義が生じてしまいます。
また監査役・監査等委員は、取締役の暴走に対するストッパーとしての役割を担っています。
監査役・監査等委員に対して、過度にストックオプションを割当てした場合、取締役の暴走に対するストッパーの役割を担わず、イケイケになってしまう可能性があると危惧されます。
例えば、監査役・監査等委員へ割当てしたストックオプションの数が、営業部門や技術部門の管掌役員等より多いというようなケースは、間違いなく議論が生じてくると思われます。
業績達成要件は?
グラスルイスの議決権行使基準2020には、次のような内容があります。
社外取締役、監査等委員である社内外取締役または社内外監査役に対しての報酬は、それぞれが務める取締役会、委員会または監査役会での活動に見合った報酬体系であるべきであり、その報酬額は、優秀な人材を確保するために、妥当な金額であるべきだと考える。具体的に言うと、グラス・ルイスは、上記に該当する役員の報酬体系としては、業績に連動しないタイプのストックオプションなどの株式報酬を含むような報酬体系を推奨する。これは、このような株式報酬を含めることにより、付与対象者である役員が、株主と同じ立場になって考えることを促し、株主の利益につながる職務遂行を期待できる報酬体系であるからである。
(出所:2020PROXY PAPER GUIDELINE GLASS LEWIS より)
監査役・監査等委員は、中長期的な企業価値向上のための役目を担っていることもあり、業績達成要件があるストックオプションの割当対象者としては適切ではないという意見が強いためです。
社外協力者・取引先へ新株予約権を割当する場合の論点
社外協力者や取引先へ新株予約権を割当てするケースは、意外にあります。
この場合の論点は、まず金融商品取引法上での論点が存在します。それにつきましては、後述する「非完全子会社の役職員へのストックオプション」で説明しています。
その他に、このような新株予約権については、主に次のような論点が発生します。
基本的には反対される
グラスルイスとISSは、2020年の段階で、両社とも明確に社外協力者や取引先に対する割当を明確に反対しています。その他の機関投資家も反対しています。
この考えは、上場審査でも、基本的な考えになっています。
なぜこの社外協力者や取引先に新株予約権を割当てすることが企業価値向上に繋がるのかという説明が必要になります。
会社の事業運営にとって、代替できない社外協力者や取引先が存在する場合はリスク
いわゆる”費用の付け替え”になっていない?
社外協力者や取引先へ支払うべき費用は、役務提供を受けた都度、支払うのが大原則です。
金銭で支払する代わりに新株予約権で支払うという行為は、上場審査上、ネガティブな判断をされます。
例えば、仕入先へ金銭による支払をせずに、新株予約権をバンバン発行することで支払に充てると、コストが激減して、収益性が高まります。このような会社の財務諸表は、正確性が乏しいと見做されることになります。
また将来の株主利益を棄損する行為に繋がる行為、つまりコストを将来の株主に行わせるという行為に繋がります。
賄賂性に繋がらないか?
例えば、A社商品を最も多く購入しているB社の購買担当者C氏に新株予約権を割当てしていたとします。
これは、接待というレベルを完全に超えています。
B社は、A社の商品力を評価して購入しているではないと疑いが出てきます。またC氏が購買担当者から人事異動をすると、A社の売上が激減するというリスクが発生します。
社外協力者や取引先へ新株予約権を割当てしていた場合、賄賂として疑われるような可能性がないかどうかが論点になります。
社外協力者へストックオプションを割当てしたものの、不適切であると判断された事例もあります。
子会社役員・従業員へストックオプションを割当する場合の論点
子会社の役職員へストックオプションを割当てすることは、よくあります。特にホールディングスカンパニーの場合は、子会社の業績がグループ全体の業績を左右するため、尚更です。
子会社の役職員へストックオプションを割当てする場合、次のような論点が生じます。
非完全子会社の役職員へのストックオプション
非完全子会社の役職員へストックオプションを割当てする場合、金融商品取引法への配慮が必要になります。
詳しくは、こちらで説明しています。
金商法違反となれば、最悪のケースとして、ストックオプションの発行から、5年間上場が出来なくなります。
また税制適格ストックオプションの要件として、議決権の50%超を保有している子会社の役職員である必要があります。連結子会社とは異なることに留意が必要です。
費用計上を求められるストックオプション
非上場会社では、滅多にない論点になりますが、費用計上が求められるような税制非適格ストックオプションを子会社の役職員へ割当てする場合、会計面と会社法面の両面で論点が発生します。
子会社側でも仕訳が発生する可能性があり、また子会社側でも株主総会と取締役会決議が必要になる可能性があります。
資産管理会社へ新株予約権を割当てする場合の論点
資産管理会社に新株予約権を割当てするケースが稀にあります。
資産管理会社に新株予約権を割当てする場合、次のような論点が発生します。
なお、どの会社が資産管理会社へ新株予約権を割当したのかをお知りになりたい方は、info@ipo-atoz.comまで。
割当数に妥当性があるか?
資産管理会社への新株予約権割当てと、オーナー社長へのストックオプション割当ては、ほぼ同じ論点が発生するものと思われます。
資産管理会社へ新株予約権を割当てしたケースは少なからず存在しますが、資本政策上での理由以外の目的、つまりインセンティブや創業者利潤が最大の目的とするものであれば、ネガティブな判断をされると思われます。また議決権の過半数を大幅に超えるオーナー社長の資産管理会社に対し、直前期や申請期に新株予約権を割当てするとネガティブに判断されるものと思われます。
顧問へストックオプションを割当する場合の論点
顧問へストックオプションを割当てしたケースは、1例だけというレアケースでした(どの会社なのかをお知りになりたい方は、info@ipo-atoz.comまで)。
しかし、顧問への付与というのは、意外と検討している会社はあります。
さらに、2019年の税制改正で、税制適格ストックオプションの適用対象者に社外高度人材(スタートアップの成長に貢献する業務を担うプログラマー・エンジニア、弁護士等)が加わったため、今後は顧問へのストックオプション割当を検討する会社が増加すると予想されます。
主な論点として、次のようなことが考えられます。
顧問の職務は?
営業面や技術面を支援する顧問を対象としてストックオプションであれば、考えられなくもないと思います。
一方、法務面や会計面、税務面での顧問に対しては、ハードルは上がると予想します。
税制適格ストックオプションの適用者として認められたことはあくまでも税務面でのことであり、上場審査やコーポレートガバナンス、資本政策とは別であるという認識が必要になります。
いわゆる”費用の付け替え”になっていない?
顧問に対して会社は、顧問契約を交わし、顧問料を支払います。
顧問料支払の代わりにストックオプションで支払うという行為は、上場審査上、ネガティブな判断をされます。
費用というのは、役務提供を受けた都度、支払うのが大原則です。顧問料の支払をストックオプションで充当する行為とは、将来の株主利益を棄損する行為に繋がる行為、つまり顧問料の支払を将来の株主に行わせるという行為に繋がるためです。
親会社役員・従業員へ新株予約権を割当てする場合の論点
ブログの中の人が確認したところ、過去5年間にあったIPOの中で1件だけ事例がありますが、ハードルは相当高いと思われます。
論点がありすぎます。
このストックオプションを審査担当者は、よく許したなあと思いますし、今後は事例がないと思われますので、取り上げることを止めました。
どの会社なのかをお知りになりたい方は、info@ipo-atoz.comまで。
入社予定者へ新株予約権を割当てする場合の論点
優秀な人材確保のため、入社予定の段階で新株予約権を割当てしようとする考えは、上場審査であまり問題にならないと思われます。
入社予定者とは、ストックオプション割当の段階では外部個人ということになるため、税制適格ストックオプションの適用対象者では金融商品取引法の観点で留意が必要になります。
もちろん、入社に至らなかった場合、新株予約権の消滅という条項は必要になると思われます。
IPOAtoZのサポート
IPOAtoZは、IPOを達成した会社の有価証券届出書からデータや事例を蓄積しています。
オンラインサロンでは、データや事例を駆使して、アレコレ議論することができます。
ぜひご参加下さい!